 AI
AI AI大喜利「一味徒党」
同じ目的を果たすために集まり、結ばれた仲間。 主に悪事に加わる仲間や集団を意味することが多い。
 AI
AI 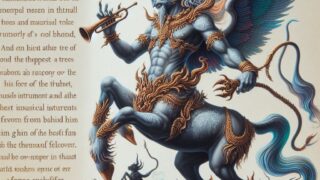 AI
AI  AI
AI  AI
AI  AI
AI  AI
AI  AI
AI 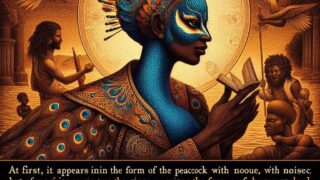 AI
AI  AI
AI  AI
AI